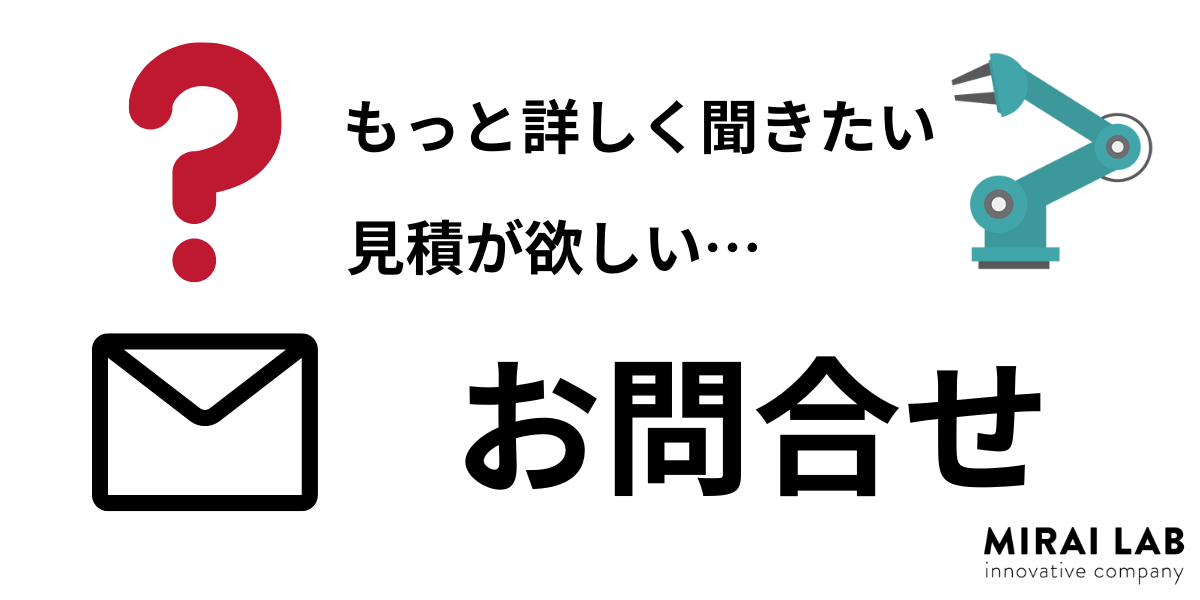皆さんこんにちは株式会社MIRAI-LABです。
今回は協働ロボットを扱うのに特別教育は必要なのか?というお話しをしていきます。

当社ではDOBOTという協働ロボットを販売しておりますがしばしばお客様から「協働ロボットは安全だから誰でも気軽に扱えるんですよね?」という様な質問を頂きます。
協働ロボットは人と接触しても人が怪我をしないような安全性が確保されているから教育を受ける必要はないのでは?と思われる方が多いのではないでしょうか?
今回の記事ではそんな疑問にお答えすべく協働ロボットを安全に扱うための基本的な考え方をお話ししたいと思います。
先に結論から申しますと協働ロボットを使うには特別教育が「必要」です。
まず前提として、産業用ロボットを扱うためには特別な教育が必要ということは弊社のロボットスクールに関する記事でご説明をしている通りです。
その根拠は労働安全衛生法第59条と労働安全衛生規則第36条という国の定めたルールに基づいています。
具体的には労働安全衛生法において危険または有害な業務に労働者をつかせるときは安全のための特別教育を行わなければけないことが定められています。
そして労働安全衛生規則で産業用ロボットの教示や検査といった作業がこの特別教育の対象となる危険な作業であることが言及されています。これらの作業は産業ロボットを扱う上で必然的に発生するため、職場で従業員に産業用ロボットを扱わせる事業者は特別教育を行う義務があるのです。
では協働ロボットについてはどのように規定がされているのでしょうか?
その根拠は労働安全衛生規則の関連通達(平成25年)が関係しており
①定格出力80W 以下
且つ
②リスクアセスメントに基づく措置を講じた場合…労働者に危険の生ずる恐れが無いと評価できる場合
これらが満たされていいることが協働作業が可能か否かの判断基準として示されています。
つまり協働ロボットというのは安全に扱う準備が整って初めて協働作業が可能になるわけです。協働ロボットだからといって安全対策をしなくていいということではないのです。
※協働作業というのは安全柵で人とロボットが隔離されておらず同じ作業空間で行う作業のことです。
従って協働ロボットは産業用ロボットとは別のカテゴリにあるかのように語られることがしばしばありますがこれは誤解で、協働ロボットは基本的に産業用ロボットと同じ扱い方をすべきロボットということになります。
このため協働ロボットを購入するお客様についても安全を守るための手段として特別教育が必要と言えるのです。
弊社では「MIRAI-LABロボットアカデミー」と称して
名古屋オフィスを活用して産業用ロボットの安全に関する特別教育を実施しております。
教材として協働ロボットのDOBOTを扱っていますので、協働ロボットを操作してみたい方や導入を検討している方、またロボットは購入したが教育は受けていない方にもお勧めです。
ご興味の方は当社のホームページや電話☎でお問合せ下さい。